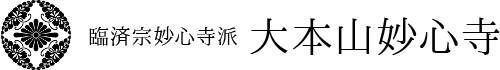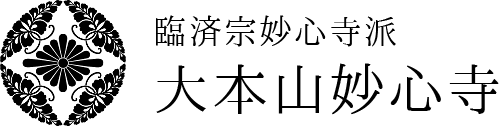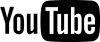令和5年度「1分で読める やさしい御詠歌解説」
~読めば花園流御詠歌をほんの少し理解できる、御詠歌のことがもっと好きになる、御詠歌への入口となるような気軽に読める無相教会準師範の先生による簡単解説です~

「宗門安心章御和讃」
後藤千衣美
宗門安心章御和讃は『宗門安心章』に説かれている教えを要約したものです。その教えとは、心静かにいつも自分を見つめ、何を信じて、何を戒めながら生きていかねばならないか、そして一日一日をしっかりと生きることがいただいた御恩に応えることであると説いた御和讃です。
御和讃・御詠歌すべてに言えることですが、お経などとはまた異なり、やさしい言葉(教え)を旋律にのせて唱えるため、無理なく自然と覚えることができ、とても心地よい気持ちになれます。
「生活信条御和讃」
安藤宗明
妙心寺派檀信徒の生活の指針を示した「生活信条」をそのまま御詠歌にしたものです。お釈迦さまの説かれた「一切皆苦」の世界に生きる私たちは、日々どのように過ごしていけば良いのでしょうか。苦しみにとらわれている自分に気づくため、静かに坐り息を調え、自他共に隔てなく、いのちのありがたさに気づき、感謝しながら思いやりの心で過ごしましょう。大いなる恵みの中に生かされる喜びを感じ、拝んでいきましょう。
この御詠歌をお唱えして、学び実践して参りましょう。
「三宝恭敬御和讃」
惠良 真由美
人は誰しも幸福を求めています。自分にとっていい日でもよくない日でも人生に意味あるものと、精一杯生きていく毎日の積み重ねこそ好日なのではないかと思います。
三宝とは仏、法、僧を意味します。仏とは人生の師、法とは人生の教え、僧とは人生の友、同心同行の衆。私たちはそれぞれとの出会いに気づくことが大切です。
この三つの宝を心の糧とし悦びを感じながらお唱え頂きたい一曲です。何に対しても執着せず、ありのままに受け容れていきたいものです。
「妙心寺開山忌御和讃」
門脇厚子
無相大師は、花園の地に妙心寺をお開きになりました。以来六百六十余年の今日に至るまで“報恩謝徳”の思いは絶えることはありません。
無相大師のご入寂の日には本山において毎年欠かすことなく妙心寺山内のご住職が総出頭して開山さま(無相大師)の法要が厳修されています。
御和讃、御詠歌ともに敬い慎む気持ちを込めるように声を出し、特に「心の花の園に栄えん」の部分は、お釈迦さま、無相大師を尊びながら、テンポはゆっくり唱えましょう。
さあ、ありがたい法灯の下、開山さまを尊びながら誇らしく、声高に唱えましょう。

「妙心寺開山無相大師伊深の御和讃・御詠歌」
開山様が、今にも目の前にお出ましになるような荘厳な御詠歌です。歌い方の難しい点は、御詠歌になってから。詩の一文字ずつを、一小節全部を使って詠じます。初めて聞くと、音としては聞こえても、詠じている内容までは分からないことが多いです。
この曲を詠ずる前に、ゆっくり朗読すると、内容が理解できるのは思います。その後、ゆっくりと詠じれば、この歌の全体的なイメージがわいてくるでしょう。
そうすれば、開山様の生きてきたご様子等を、目に浮かべて頂けるのでは無いかと願っています。
「追善御和讃・御詠歌」
追善御和讃は、通夜・葬儀・年忌法要等でよくお唱えされる御詠歌です。追善とは、先亡の精霊に対して供養仏事を行うことを言います。この御詠歌をお唱えしますと、亡き人の面影が自然と浮かんでまいります。この世は無常ですが、せめて死後の旅路が安らかでありますように、どうか仏さまのともしびでみたまを照らしてくださいと願いながらお唱えしたいものです。お唱えしているうちに、鉦の音や鈴の音が自然に心にしみわたり、だんだんと心が静まってきます。生死そのままが安楽の世界であるとお釈迦さまはお示しくださいました。迷いの世界を越えて生きようと誓うことこそが、最高の供養となることでしょう。

「妙心寺開山無相大師御入定御和讃」
妙心寺の開山さまのご命日は十二月十二日です。その日の雪が舞う様子を、「雪の花ちる十二日」と表現されたのが絶妙です。加えてメロディも、はらはらとまた、しみじみと唱えるようさざなみの記号となっています。ゆり記号もまた、時の流れや生き方の尊さを味わうものです。詠歌の「藤のつる輪」の「る」の音の落ちは釣瓶の井戸の桶が落ちていく様であり、その後引き上げられる時、水の重みが加わる故に輪の音は、なえしの記号となっていることに注目しましょう。風水泉のそばで、心静かに立亡されたお姿を偲びつつ、心を込めてお唱えしたいものです。
「彼岸会御和讃」
「和っさん!私、御詠歌をお唱えするようになって、死ぬことが怖くなくなったわ。私がもしもの時は、良いとこに連れていってくれるんやろ?」当時御詠歌に来られていた八十二歳の講員さんがおっしゃいました。私は咄嗟に「まかせといて!」と、応えました。
「いざ行かん 行きて彼岸の花を見ん生死の海は波あらくとも」
みんなでお唱えをして、みんなで修行すれば、きっと毎日が力強く生きられる。恐れることはない。良い世界(彼の岸)に行けるのだから。 おばあちゃんのその姿勢と心こそが、悟りの花を見ておられるように感じました。

「釈迦如来御誕生御和讃」
東海裕子
四月八日は、仏教の開祖お釈迦さまが御誕生になられた日です。お生まれになると、お釈迦さまは四方に七歩ずつ歩まれ右手で天を左手で大地を指さして「天上天下唯我独尊」と一人一人が尊い命を持ってこの世に生まれてきたことを叫ばれました。人々のあらゆる苦しみをお救いくださるお釈迦さまです。この尊いお釈迦さまの御誕生を、心からお祝いし、明るい気持ちでこの御詠歌をお唱えしたいと思います。
「釈迦如来成道御和讃」
都竹隆雄
この曲はお釈迦さまが四苦(生老病死)を解決するために出家を決意され、六年間の難行苦行の後、それでは成果は得られないと気づき、ブッタガヤの菩提樹の下で坐禅、そして十二月八日暁の明星が輝くのをご覧になり、大いなる悟りの境地に至るまでの過程がわかり易く説いてあり、またお釈迦さまが身をもって証明された「皆、平等に誰でも努力をすれば必ずお悟りが開ける」という永久不滅の真理「無上正覚」も表されています。
全体の曲調は唯一無二で、序盤からクライマックスへの導入も秀逸であります。しみじみと心を込めてお唱えしましょう。

『正法山妙心寺第一番の御詠歌』
清水寿晴
大本山妙心寺の山号は、正法山です。その山号の由来がこの曲に説かれています。
ある時、お釈迦さまが無言の説法をされ、聴衆の1人であった、迦葉尊者だけがお釈迦さまの御心をくみ取り、にっこりと微笑みました。お釈迦さまは「我に正法眼蔵、涅槃妙心、実相無相、微妙の法門あり・・・」と言われました。そのお話が正法山妙心寺の名前の由来です。
インド霊鷲山でのお釈迦さまの説法は、2,500年以上たった今も、花園法皇さまゆかりの妙心寺境内の松に届いています。
「目連尊者御和讃」
醍醐千草
歳を重ねるにつれ、徐々に心に染み入るのがこの曲です。
他にはない構成になっていて、和歌の上句と下句の間に御和讃が有ります。古歌なので、その意図は想像するしか無いのですが、万葉集のような素朴さがあり、深い郷愁を誘います。亡き人を想う心を和歌に込め、目連尊者の逸話を挟むことで自然にお盆の大切さに気づかされるのです。目連尊者はお釈迦様の十大弟子の一人です。お釈迦様と出会い、餓鬼道に落ちた母を救うことができました。これが盂蘭盆会の始まりです。この御詠歌は施餓鬼会(せがきえ)の際にもお唱えされます。

「花園太上法皇第一番の御詠歌」
津田玲子
法皇さま御自ら詠まれたお歌です。戦の絶えない不安な世を生きていく民衆を思いやる御心が詠まれています。三拍、五拍の鈴唱も難しいですが、声や節の善し悪しにとらわれず、心を込めて唱えることが大切です。
「三昧にならにゃいかんよ。一生懸命に唱える、それだけ!」と先生に教えていただきました。こころに響く御詠歌です。一生懸命なお唱えが心の杖(支え)になってくれることでしょう。
「妙心寺二世微妙大師第二番の御和讃」
吉田拙堂
微妙大師、大悟徹底の心境を詠った御詠歌であります。唱え方は、ゆったりと重々しく丁寧に一音一音刻んでいくように。そして節を大切にすることを心がければ、悠々自適のご心境が味わえると思います。
後半「世のうさを」からは陽音階となるので、軽やかな気持ちで爽やかにお唱えできると思います。最後の「やまずみのとも」は低音となるのでしっかりとした声が出るように、最初から(詠題から)の本数に注意をしましょう。 この御詠歌は詠歌三昧の心境を味わえる名曲だと思います。

「妙心寺再興雪江禅師御和讃」
中世の応仁の乱、繰り返された戦いで町は焼かれ、人々は傷つき、大切なものを失いました。妙心寺も大半が灰燼と帰してしまいました。しかし、目に見える物は失っても人の心まで奪うことはできません。
そんな中、雪江禅師は粉骨砕身、妙心寺再興のために力を尽くされ、伽藍を再建し整備されました。
幼い頃から強い信仰心を持ち、修行を重ね意志を貫き通された雪江禅師。妙心寺は再び春を迎え、その教えは500年余り経った今日まで受け継がれています。
雪江禅師のお徳を偲び感謝の気持ちを胸に世の中の平和が実現することを願いつつ、お唱えしたいと思います。
「妙心寺中興開山日峰禅師御和讃」
妙心寺には室町時代に寺領はもとより一切の財産を没収されたこと(応永の乱)がありました。30余年後、妙心寺復興の兆しが表れその大任を果たす高徳の僧侶として後に中興開山となる日峰宗舜禅師が屈請(くっしょう)されました。日峰禅師は幼少期より聡明で9歳で仏弟子に。仏心篤く厳しい修行を積まれ、清水湧く内田の地に青龍山瑞泉寺を開創いたしました。瑞泉寺では日峰禅師により妙心寺法灯再興の力が蓄えられ63歳で妙心寺入山を決意。荒れ果てた妙心寺復興に力を尽くされました。
御詠歌では、凛とした格調高い節回しと共に『再興苦難の道』と『法の花が今も盛りと咲き誇るさま』がありありと唱えられています。

「延命地蔵御和讃」
正山照子
優しい微笑みをたたえ、悩み迷う私たちを見守りお救いくださるお地蔵さま。その御心を詠んだ御詠歌です。
発想記号に「優雅に」とありますが、お地蔵さまのように「慈悲の心」で優しくお唱えください。和讃の頭はシの音から始まります。詠題から正しく音が取れるように気をつけましょう。細かいリズムや低い音の音程などが崩れないようしっかりお唱えしましょう。
鈴鉦は変則的です。拍や節と合うようゆっくり、正確に繰り返し練習してください。特に撞木は、高さや動き、流れに注意しましょう。
詠歌は、他の御詠歌にもある大慈節ですが、詞の内容を深く理解し「延命地蔵御和讃の大慈節」をお唱えできるよう心がけておけいこしてください。
「達磨大師御和讃」
木村はるみ
禅宗の御教えをよくご存知ない方々でも「ダルマ」という名は七転び八起・必勝祈願等々で皆様周知のことと思います。達磨大師とは南インド香至国で御誕生になり、修行をつまれ仏教の二十八祖、禅宗の初祖となり中国に渡り禅の教えを広められました。梁の武帝との禅問答、少林寺で面壁九年座禅を続け、悟りを開かれました。そのみ教えが中国全土、日本に伝わるまでを説いた御詠歌です。
面壁九年、粘り強くただひたすら黙して坐り続けた大師のお姿。自身の腕を切り落としてまで師事することを懇願した慧可という弟子の存在。
様々な物が満ち溢れている現代社会の中で忘れてしまいがちな忍耐・辛抱の大切さ。七転八倒しながら生きている私には、その尊い御教えを感じずにはおられない一曲です。

『生活信条御和讃』
畠中八代江
生活信条は、すべての人の生活をこころ豊かにとお示しされたものです。
今一度、生活信条を思い出してみましょう。
この曲は、昭和37年に和久弘昭師範がわかりやすく御詠歌の歌詞にされました。
御詠歌を唱えるポイントは、「世にあえば」の「に」㋑、「いちどは」の「ち」㋑の母音の長さ8分の1の表し方の所に気をつける。詠歌の最後の歌詞「掌を合わすかな」は自分も他人も自然と掌を合わしたくなるようにお唱えしましょう。そのためには、『ただ…ただ』の強弱も大切です。
生きているということは、多くの方のお世話になっているということ。報恩謝徳の心をいつまでも持ち続けていきましょう。
【4月15日更新】