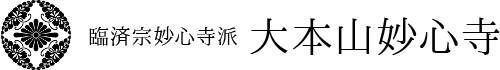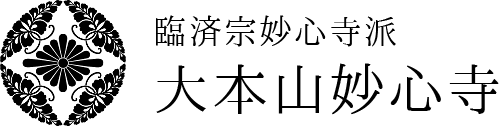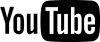「枇杷にまなぶ」
今年は嬉しいことがありました。庭の枇杷の木がはじめて実をつけたのです。とても美味しい枇杷だったので、ダメ元で蒔いた種から生えた木です。木は大きくなったものの、去年まで花も咲かず実もつけませんでした。やはりダメかと諦めていました。ところがこの春、三本のうちの一本に、二十年近く経ってやっと花が咲き、沢山の実がなりました。嬉しくて「ありがとう、ありがとう」と、何度も木肌を撫でたことでした。
枇杷といえば、夢窓疎石禅師の『夢中問答』に面白い話があります。枇杷の時期、清水寺に日参して観音さまに何ごとかを祈念している老尼がおりました。あまりに熱心なので近くの人たちが奇妙に思い、「一体何をお願いしているのか」と尋ねます。すると老尼はこう言いました。
「私は若い頃から枇杷が大好きだけれど、枇杷はあまりに種が大きくて食べるところがない。そこで、種をなくして欲しいと観音さまにお願いしているのです。でもまだ一向にそのしるし(霊験)がありません」
それを聞いて「そんなこと、観音さまにお願いするほどのことか」と大笑いしたというのです。
この話に対する夢窓禅師のコメントは、「お経や陀羅尼を唱えて、世間的な幸せを願い災難を逃れようとするのも、この老尼の祈りと何ら変わらない」と、大笑いをした人たちを諫めるものでした。枇杷好きの私には老尼の気持ちは痛いほどわかりますが、夢窓禅師のお諫めには反省しきりです。夢窓禅師は「しるしなきこそしるしなりけり」とも仰ってます。霊験がないことが霊験なのだと。
日々私たちは神仏に祈り、願いを掛けます。その祈りや願いが叶ったら嬉しいですね。でも、考えてみてください。もし一つの願いが叶えば必ず次の願いを「叶えて下さい」と祈るのではないでしょうか。これは一種の欲望の再生産に繋がります。「この欲望の再生産こそ私たちを仏さまから遠ざける要因なのだ。だから神仏が祈りの霊験を示さないことこそ霊験である」。これが夢窓禅師の真意です。
菅原道真公は
心こそ誠の道に叶いなば 祈らずとても 神や守らん
と詠んでいます。一休禅師はこれをもじって
心こそ誠の道に叶いなば 守らずとても此方(こち)はかまわん
と詠みました。誠の道とは抽象的でわかりにくいですが、欲望の再生産にハマり込まないような生き方と言い換えてみたらいかがでしょう。仏さまにお参りするときは、頼みごとの代わりに、心穏やかに「おかげさまで」「ありがとうございます」と言う。周囲の人にもそういう気持ちでお付き合いをする。そんな日々を送ることができたら、争いもなくなり、きっと仏さまに近づけると思うのです。
「仏道無上誓願成」(仏(さとり)の道はこの上ないものだけれども、誓って成し遂げんことを願う)が今年の推進テーマですね。私も道真公の歌をこんな風に読み替えてみたいと思います。
心こそ誠の道に叶いなば 願わずとても仏なりけり
枇杷の木も種々の困難を経て、日々成長を続けていたに違いありません。そして機が熟して結実してくれました。私たちも何時の日か仏になるように、誠の道、仏さまの道に叶う日々の暮らしをしていきたいものです。
竹中智泰