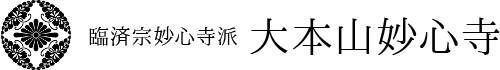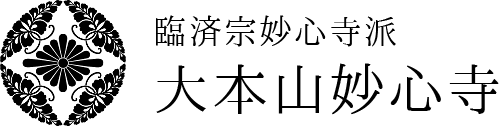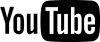【清泉】ありゃー 生きとったか(2013/10)
昭和二十三年秋、愛媛県南西部の中川村という小さな村で、私は八ケ月の早産で生まれました。今日なら保育器入りでしょう。
「上に二人も男の子がいるのだから。母親を助けるに決っとるわな......」と、
母親は病気のため、親を助けるか、子供の命を助けるかと医師と家族の間で評定がなされたようです。
母親の手当てを終え、ようやく微かに泣き声をあげる未熟児を、七十を過ぎた祖父母が僅かに蓄えていた米で、上澄みから次第に重湯になるまで与え続け、育ててくれました。
私は、母親の母乳から免疫を受け継がなかったので、いくたびも生命の危機に瀕したそうです。
その都度、医師は枕元に駆けつけ、
「今夜あたり心配やなあ。何ぞあったら来てやるぞ」と言って帰られ、翌朝は診療前に必ず駆けつけ枕元までやってきて、
「ありゃー、生きとったか」
そんなことがあったからでしょうか、私がおたふく風邪に罹った三年生の時に病室に入るや、医師は抱きしめんばかりに大喜びでカメラを取り出し、裏庭にいざなって写真を撮って下さったのです。
「あんたがなあー、よう育ったもんやなあ」と嬉しがっています。
その時代には、幾人もの人が必死の看病の甲斐もなく、この世を去られました。そのため先生には、「ヤブ」の中傷もありましたが、労を惜しまず駆けつけて下さいました。
晩年、懺悔の思いと追悼の気持ちを、地蔵堂建立に託されたご芳志を思う時、本当に良医であったと思います。
戦後の薬も満足にない時代に未熟児で誕生し、ろくな食物にも預らず、今日までこの世に命を永らえてこられたのは、今は亡き先生のおかげだと感謝と追慕の念しきりで、私にとって一番大切な命さえ、この私1人のものではないと感謝し、生きていきたいと思うのです。
〜月刊誌「花園」より
小田実全(おだ じつぜん)