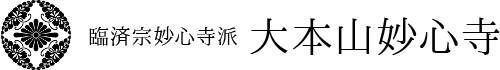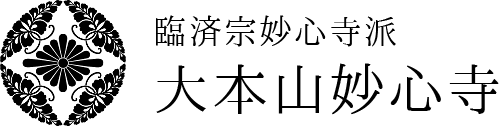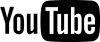明月来リテ相照ラス

昼間の残暑はまだまだ厳しい季節ですが、朝晩のひんやりとした風や、表を歩いて草露に濡れる足元は確かに、秋の訪れを感じさせてくれます。空を眺めれば暑かった夏とは様子が異なり、もこもことした鱗雲が現われます。そんな秋の空に、夜になるとぽっかりと浮かぶのが「月」です。そうです。「仲秋の名月」の時節到来です。満月は毎月のようにありますが、秋の澄んだ夜空に特に美しく浮かぶこの日は、昔から願いを込めて祝い事や、行事がなされてきました。
「月」は古来から別世界の象徴でした。現世の苦悩が大きければ大きいほど、その憧れは一層増します。それと同時に、清く、さやけく、冷たく澄んでいる月が返って濁り厚き人の世をなつかしく思わせます。争いの耐えない人の世。ねたみや憂い、喜怒哀楽に満ちた世の中。そんな世を、月の光は優しく照らします。
月明かりの夜は、色という色が消え、変化します。それが一体なんなのか見分けがつかないくらい。確かに、小学生だった頃、満月の夜に近所の子供たちで集まって、紙に色マジックで線を引き、色当てゲームをして楽しんだ記憶があります。今でこそそれは視覚器官の錯覚だと言うこともできますが、すべてのものが同じ光で包み込まれ、お互いがいつもと違って見えると、全ての垣根が薄くなっていくような、そんな感覚を満月の夜は感じさせてくれました。あたり一面月の色、隣の子の顔も向かい側のおじちゃんも、紙もマジックも、カエルも虫も、そしてもちろん月も私も。燃えたぎる感情や、冷え切った感覚まで、月の光がみんなを一つにしてくれます。
ある月夜ことごとく籠の虫を放つ 正岡 子規
これは明治29年の秋の句です。子規は結核を患い36歳で亡くなります。この年はその結核が悪化し、菌が脊椎を巣食ってカリエスという病にかかった時です。
籠の中から放たれていく虫たち。「ことごとく」という言葉から虫は、様々たくさんいることがわかります。飛び跳ねる虫、這い回る虫、大きい虫、小さい虫...。病が悪化し、臥床の日々が多くなり、せめて外にいる虫を籠に入れて眺めていたのでしょう。しかしその虫たちもいずれ放たなければなりません。それが月夜の晩だったのです。すべてのものが同じ光で包み込まれる日、子規は月の光に照らされた虫を眺めながら、そして自分も照らされながら、自分と虫を重ねていったのでしょうか。虫たちそれぞれの解放は自分の苦しみからの解放を願ってのことかもしれません。虫たちとの隔たりが淡くなった子規もまた、月のような光を放っています。
月は遍く全てのものを照らしてくれます。男も女も老いも若きも、恋するあの人も、憎きアイツも。暑さも過ぎ去った月のきれいなこの季節、静かに空を見上げて、全てを照らすその姿に自分を見つけてみてはいかがでしょうか。
窪田顕脩